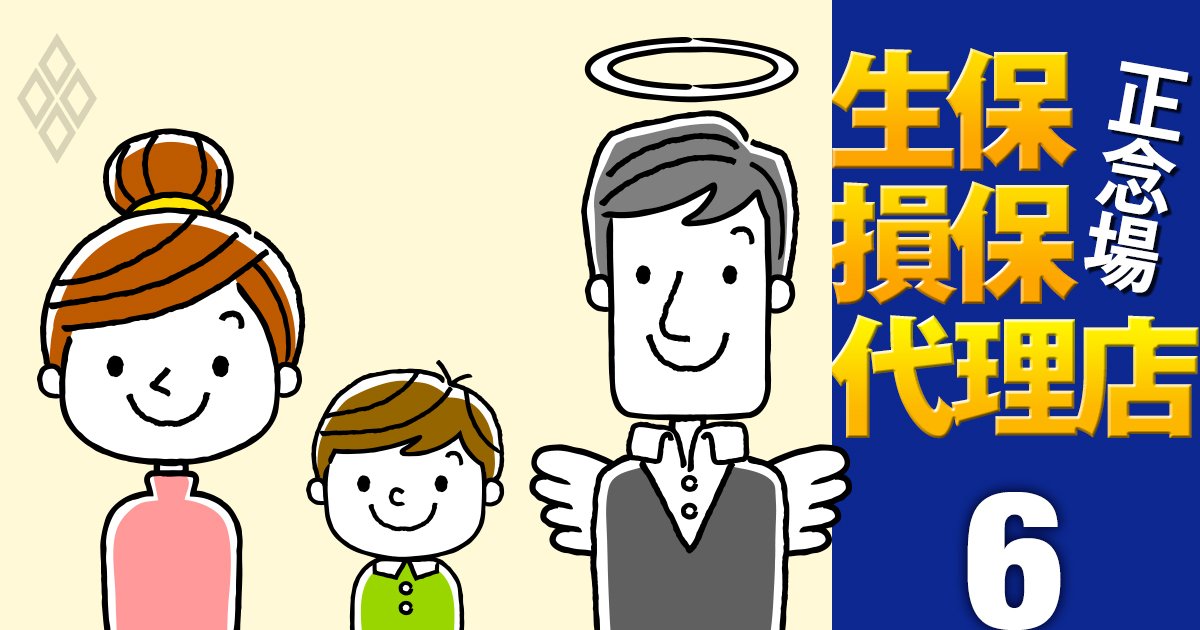米中貿易摩擦の激化や新型コロナウイルスの感染拡大──さまざまな外的要因によって、サプライチェーン(供給網)の見直し、調達業務のオンライン化に取り組む製造業の数が増えている。テクノ・システム・リサーチの調査によれば、オンライン機械部品調達サービス市場は2020年時点で利用ユーザー数が9万3400件増加、前年比153%で成長しているという。
そうしたニーズの高まりを受け、成長を遂げているのが製造業の受発注プラットフォーム「CADDi(キャディ)」を提供するキャディだ。
CADDiは独自開発の原価計算アルゴリズムをもとにした自動見積もりシステムによって、メーカーが希望する品質・納期・価格に最も適合する加工会社を選定してくれるサービス。メーカー(発注者側)はこれを使うことで、従来何週間もかかっていた相見積もりの負担や複数サプライヤーの管理工数を削減でき、最適なサプライチェーンが構築できる。
一方の加工会社は受注率約2割の相見積もり作成作業や定常的な価格低減の交渉、一社(一業界)への売上依存体質による売り上げの不安定化といった課題が解決できる。
発注者側の利用企業は全国約1600社(2021年5月現在)を突破しているほか、提携加工会社は600社以上という規模になっている。キャディ代表取締役の加藤勇志郎氏は「直近のCADDiの受注高は昨対比で約6倍に成長している」と語る。