
良いものを作れば売れる──そんな考え方は今や“前時代的”なものとなりつつある。ヒット商品が生まれればすぐに模倣され、飽きられるスピードも早くなっている時代において“機能性”で差別化を図るのは難しい。人もモノも埋もれる時代の中で、新しい稼ぎ方として注目を集めている概念が、プロセス自体を売る「プロセスエコノミー」だ。
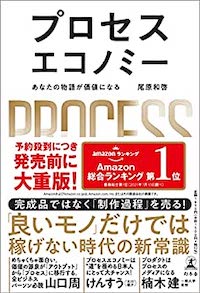
商品の機能や性能で差別化できなくなったからこそ、その人が持つ“こだわり”や“哲学”が反映されたプロセス、制作過程を売る。2021年7月に『プロセスエコノミー あなたの物語が価値になる』(幻冬舎)を出版した、IT批評家の尾原和啓氏は「プロセスエコノミー的な考え方はこれからを生きるすべての人に関係がある話で、特別な人にだけ必要な概念ではない」と語る。
ここ1年の間で耳にするようになった「プロセスエコノミー」とは一体何なのか。その正体について、同書の内容を一部抜粋してお届けする。
プロセスエコノミーとは何か?
もはや完成形で差をつけるのってしんどい。そんなことを感じたことはありませんか? このような人もモノも埋もれる時代の新しい稼ぎ方が、プロセス自体を売る「プロセスエコノミー」です。なぜならプロセスはコピーできないからです。自分のこだわりを追求する姿、様々な障壁を乗り越えながらモノを生み出すドラマはその瞬間にしか立ち会えません。
本当に自分がやりたいことをやって、作りたいものを作って生きていくために、プロセスエコノミーは強力な武器になります。このプロセスエコノミーは私が考えた言葉ではなく、クリエイターの制作現場をライブ配信する「00:00 Studio」(フォーゼロスタジオ)を立ち上げた「けんすう」さんが初めて言語化しました。
プロセスエコノミーという聞きなじみのないカタカナ言葉を、どこかとっつきにくい、難しいと思ってしまう人もいるかもしれません。しかし、この本を手に取り読んでくださっている皆さんも、きっと生活のどこかにプロセスエコノミーを取り入れているはずです。
プロセスエコノミー的な考え方はこれからを生きるすべての人に関係がある話で、特別な人にだけ必要な概念ではないのです。




