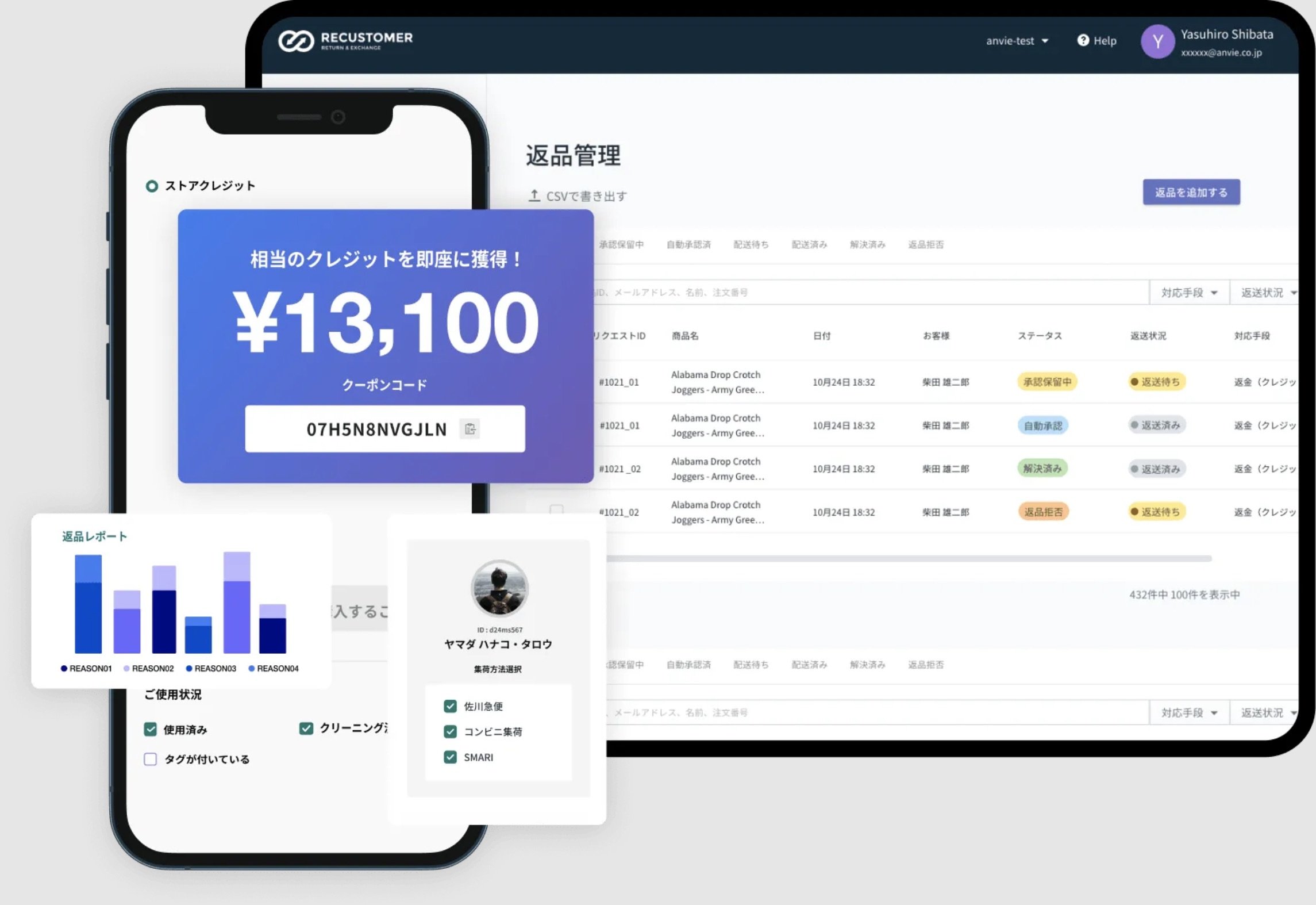
ECが普及すればするほど、事業者を後押しするようなサービスや消費者の購買体験をより良くするサービスのニーズが高まり、そこに新たなビジネスチャンスが生まれる。
一見地味に思える「商品の返品業務・返品体験」のアップデートもその1つと言えるだろう。
EC小売業の返品率が数%程度と言われる日本ではまだそこまでの注目を集めるには至っていないが(エルテックスが実施した「通信販売事業関与者の実態調査2021」によるとEC/通販の商品返品率は5~10%がボリュームゾーンだという)、この数値が25〜40%ほどとされる米国ではここ数年で明確な変化が生まれている。
Amazonでは2016年より出品者に対して返品無料を義務付けており、ZARAのようなファッションチェーンやAllbirdsを始めとする勢いのあるD2C企業などもこぞって返品無料ポリシーを掲げる。
背景として、ユーザーにとって返品ポリシーの存在がECサイトを選ぶ際の重要な指標の1つになり始めていることがある。また、返品したユーザーの一定数が「返品時に追加で商品を購入していること」が複数の調査などでわかってきたことも大きい。




