
社会人7年目──“29歳”という異例の若さで、東証一部上場企業の日本事業の総責任者に就任した人物がいる。クックパッドJapan CEOの福崎康平氏だ。
料理レシピの投稿・検索サービス「クックパッド」や生鮮食品のネットスーパーサービス「クックパッドマート」などを展開するクックパッド。2013年から海外展開し、現在は76カ国・地域、34言語でサービスを展開している同社だが、収益の9割以上を稼いでいるのは日本事業。福崎氏はそんなクックパッドの日本事業のトップとして、2020年9月から会社の舵取りをしている。
クックパッドは2016年に創業者であり取締役兼執行の佐野陽光氏と穐田誉輝氏(現:ロコガイド代表取締役)が率いる旧経営陣との経営方針をめぐる“お家騒動”によって、株価が低迷。2019年度には上場以来、初の赤字に転落した。そうした背景もあり、クックパッドが日本事業の総責任者に“29歳の若手”を抜てきしたことは世間から大きな注目を集めた。
だが、同社はいま壁にぶつかっている。2021年度は第1四半期(1〜3月)の最終損益が3億4900万円の赤字だったのに続き、第2四半期(4~6月)も6億7000万円の赤字だったと発表した。月額308円(税込)のプレミアムサービス会員は第1四半期と比較して、約9.2万人減少するなど、“クックパッド離れ”が進んでいる。
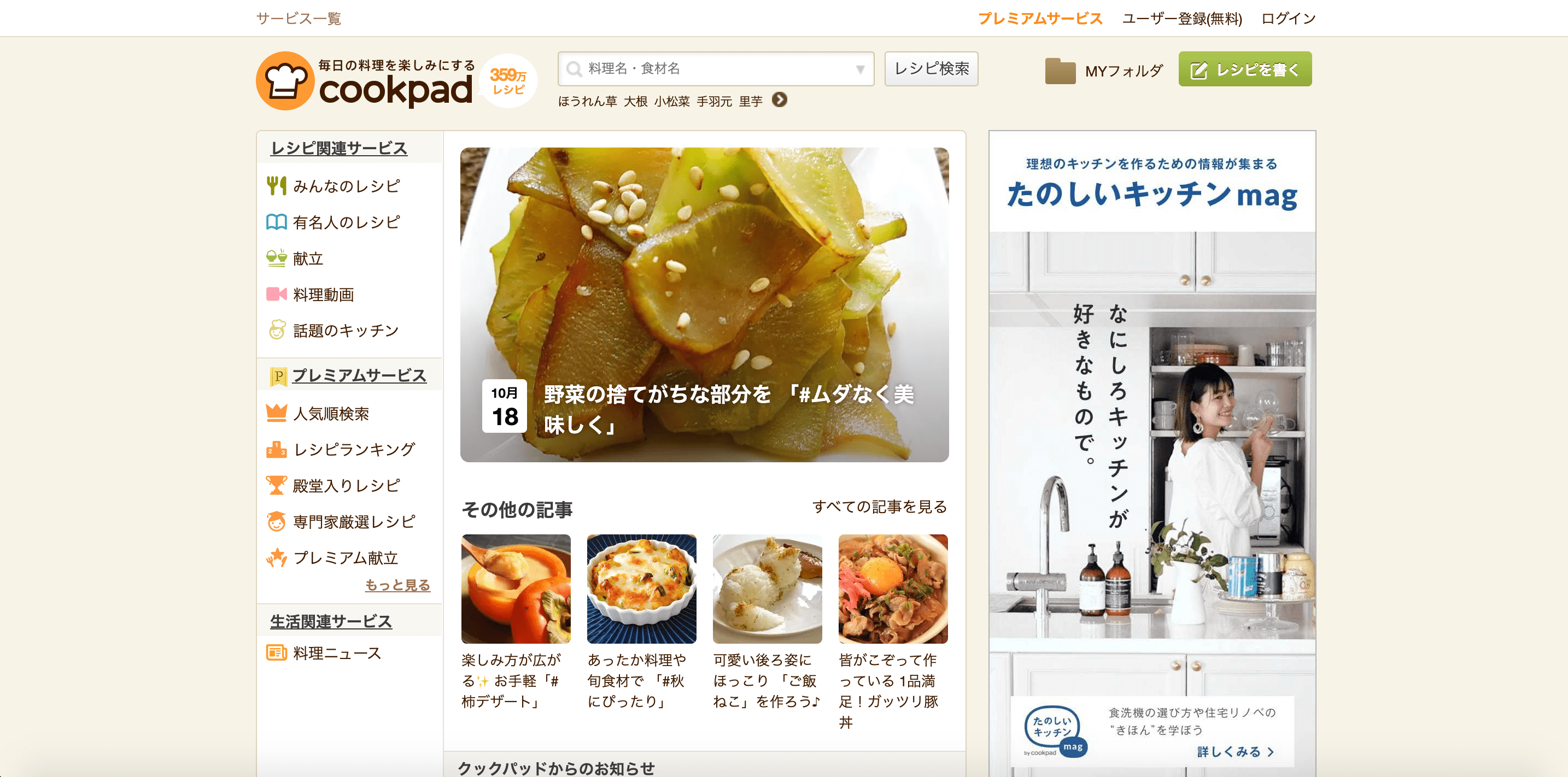
会社の立て直しに向け、福崎氏は「クックパッドは今後、『レシピ』の会社から『料理』の会社へと変わっていきます」と語る。クックパッド復活に向け、事業を統括する福崎氏は会社の未来をどう描いているのか。「食堂」の運営から始まったキャリアをもとに、彼が考えるこれからの「食のあり方」をひもといていく。




