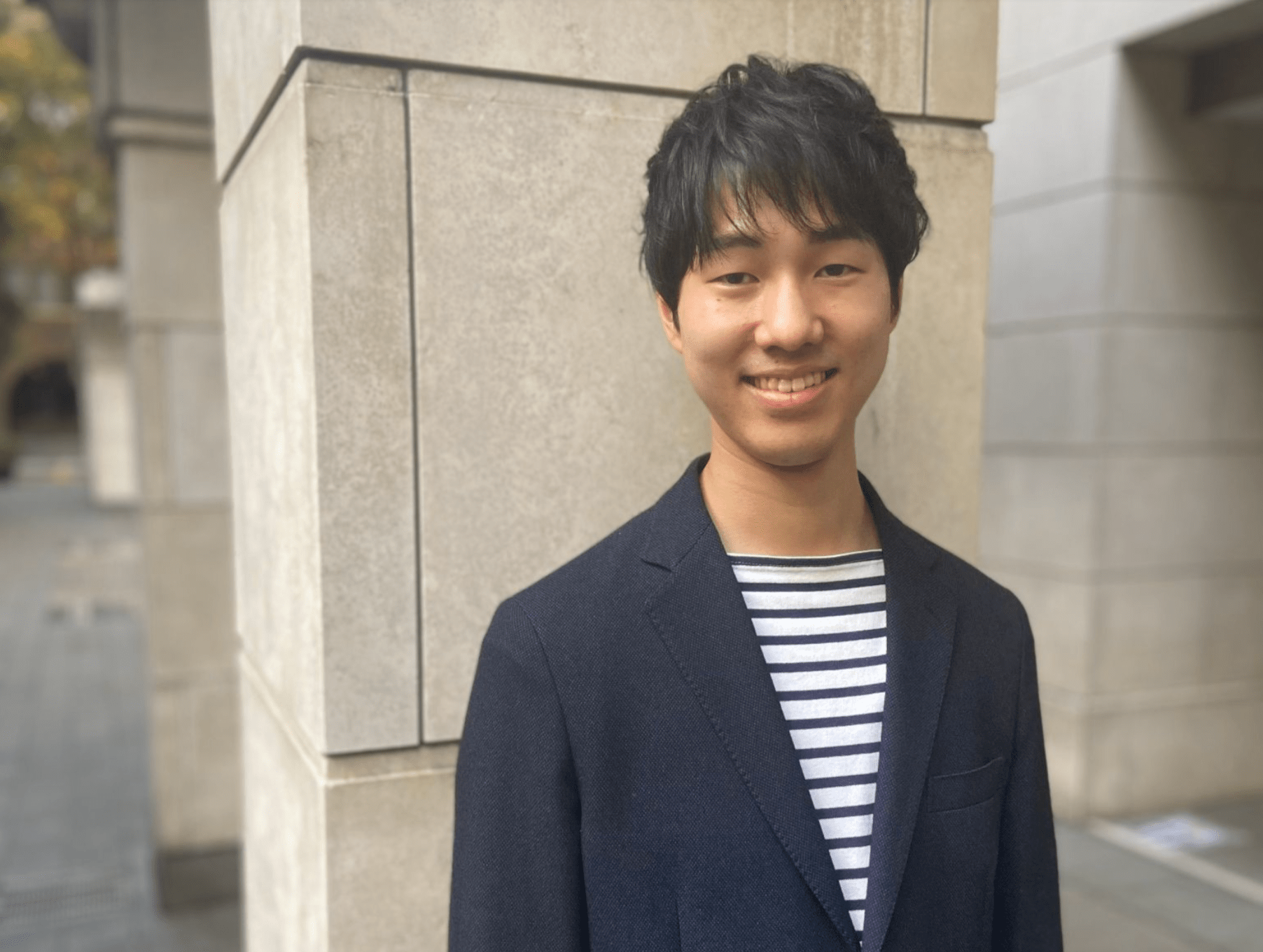
現役の東大生が「子どもに読書を好きになってもらうこと」を目指して開発したオンライン習い事サービスが、地道に利用者を増やしている。2020年創業のYondemyが運営する「ヨンデミーオンライン」だ。
サービスの特徴は、子ども一人ひとりの好みや読む力に合わせた本を“AI司書・ヨンデミー先生”がおすすめ(選書)してくれること。本の楽しみ方が学べるチャット形式の対話型学習コンテンツや、ゲーム要素を取り入れた読書のモチベーションを高める仕組みも提供することで、子どもが読書に夢中になるように仕掛ける。
カギを握るのがAI司書による選書の精度だ。その精度を上げるためにYondemyのメンバーたちが自ら「1000冊以上の児童書」を読み込み、独自のデータベースを構築している。
2020年12月のサービス開始から1年弱、無料体験ユーザーを含めて1400人以上がヨンデミーオンラインを受講した。月額2980円の有料会員も増加傾向にあり、さらなる成長を見込んでいる。
そのための資金としてYondemyではXTech Ventures、D4V、W ventures、F Venturesを引受先とした1億円の資金調達を実施した。今後は組織体制を拡充し、子ども向けアプリの機能拡充や保護者向けアプリの開発などを進めていくという。




