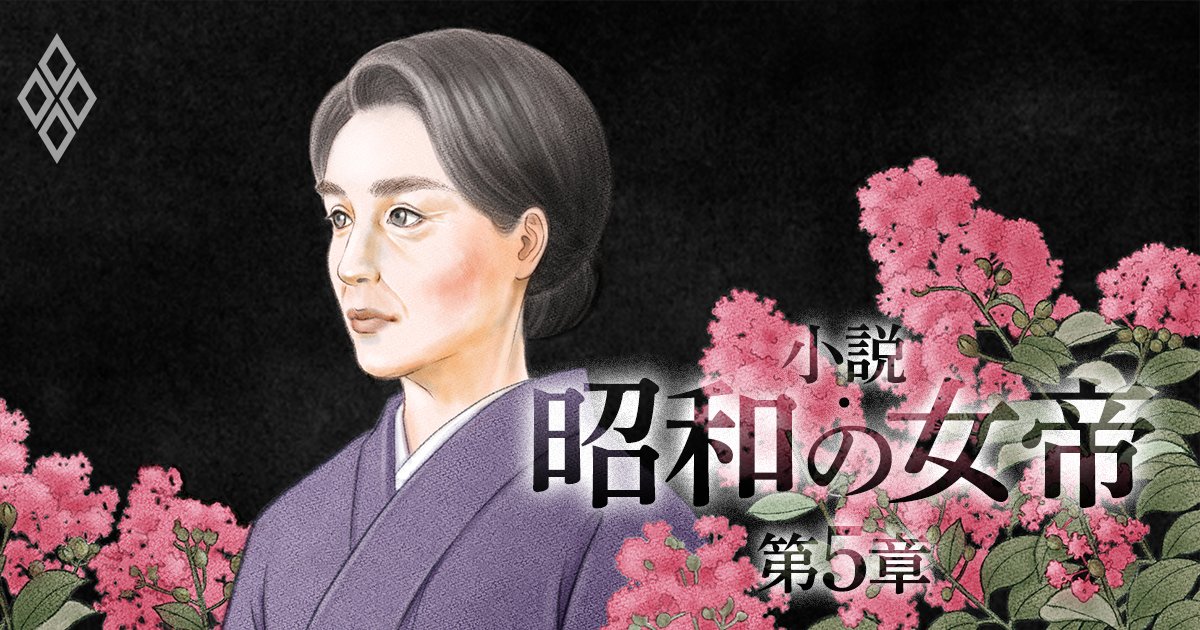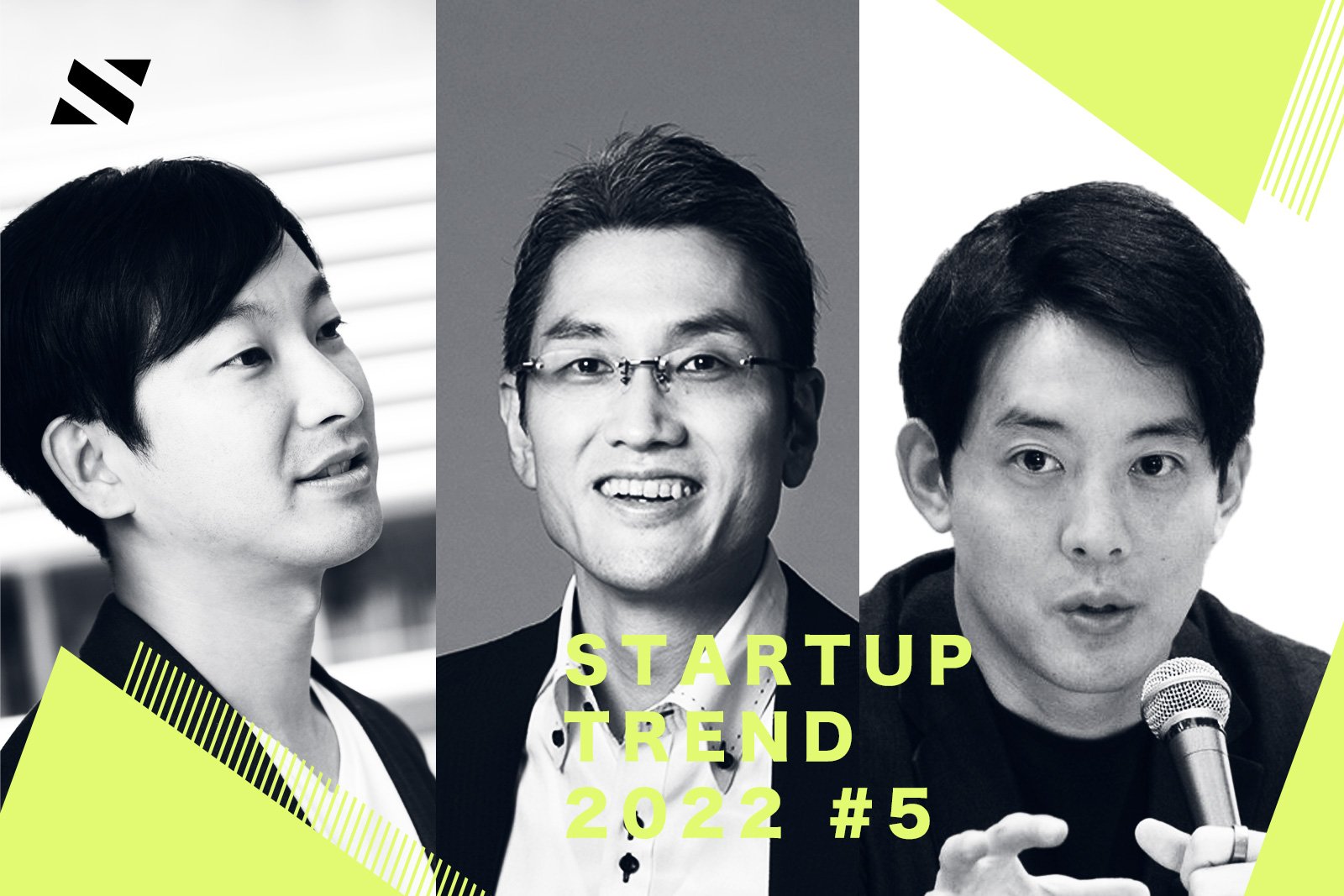
2020年に引き続き、新型コロナの影響を大きく受けた2021年。人々の生活様式はさらに変化し、その影響は大企業からスタートアップまでを巻き込んでいる。果たして2022年はどんな年になるのか。
DIAMOND SIGNAL編集部では昨年と同様に、ベンチャーキャピタリストやエンジェル投資家向けにアンケートを実施。彼らの視点で2021年のふり返り、そして2022年の展望と注目の投資先について語ってもらった。第5回はTybourne Capital Management マネージングディレクター/日本株投資責任者 持田昌幸氏、ジャフコ グループ パートナー 藤井淳史氏、シニフィアン 共同代表 朝倉祐介氏の回答を紹介する。
Tybourne Capital Management マネージングディレクター/日本株投資責任者 持田昌幸
2021年のスタートアップシーン・投資環境について
2021年も引き続き、スタートアップへの資金流入はグローバルで続き、日本においてもスタートアップの資金調達額が過去最高になる見通しです。これにはさまざまな要因が考えられますが、日本のスタートアップのエコシステムが確実に成長し、海外を含めた投資家もこれらを確実に評価した結果だと言えます。
一方、投資環境という観点では、私たちのようなクロスオーバー投資家としては、未上場市場だけでなく、上場市場の動向を見ることも重要です。特にスタートアップの多くがIPO先として利用するマザーズ市場は2021年初以来マイナス16%(12月24日現在)とパフォーマンスは良くありません。また2021年に上場した企業の中には、株価が公募価格を下回って推移するケースも散見されるようになってきました。上場市場の株価が常に企業の本質的価値を示しているわけではありませんが、これらは、少なくとも一時的に上場市場と未上場市場に温度差があることを示しています。
2021年、私が日本株投資責任者として注目していたフィンテックやSaaS分野は、2020年に引き続き大きく盛り上がったと感じています。特に、私たちも株主として携わっていたPaidyのPayPalへの売却は、日本のスタートアップに新たなExitのオプションを提示しただけでなく、グローバルプレーヤーが日本のスタートアップ企業の買収に興味があることを示したという点でも非常に意義深かったと感じています。
今後、IPO時にM&Aの売却プロセスを走らせ、上場と売却、どちらのオプションが高い企業価値を提示するのかを見るデュアルトラックプロセスが増えるでしょう。これは、ストラテジックアセットであればあるほど重要度を増し、株主価値最大化を果たす上でもなくてはならないプロセスであると考えます。
また、2021年は日本でもこれまでより多種多様な手段で資金調達が行われた年だったと感じます。スタートアップ企業の調達方法の多様化は、企業に経営の柔軟性を与え、マーケットの活性化を促します。スタートアップがデットで調達できる額は着実に増えています。今後スタートアップのCFOはエクイティの調達だけでなく、銀行、クレジット投資家のハンドリングが必要なスキルになっていくでしょう。