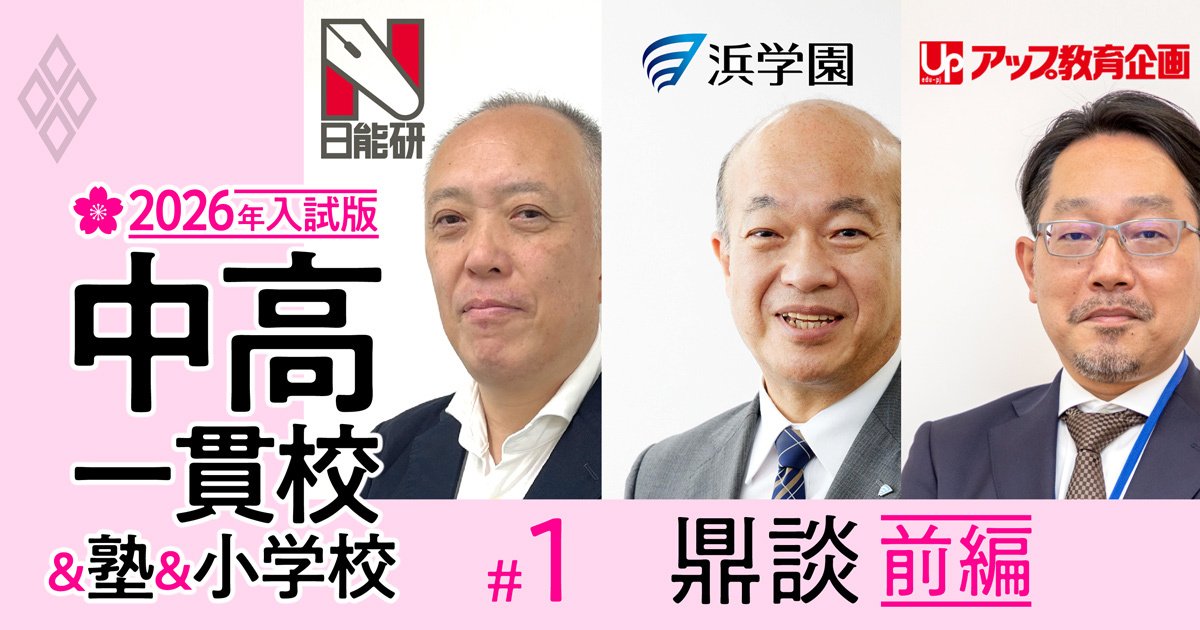資金調達にサービスの立ち上げ、上場や事業売却と、ポジティブな側面が取り上げられがちなスタートアップだが、その実態は、失敗や苦悩の連続だ。この連載では、起業家の生々しい「失敗」、そしてそれを乗り越えた「実体験」を動画とテキストのインタビューで学んでいく。第4回はさくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕氏の「失敗」について聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部副編集長 岩本有平、動画ディレクション/ダイヤモンド編集部 久保田剛史)
さくらインターネットの創業は1996年。当時、舞鶴高専の生徒だった田中邦裕氏が、共有レンタルサーバサービスを個人で始めたのがそのルーツだ。1999年には株式会社化して東京、大阪にそれぞれデータセンターを開設。事業を本格化した。
 さくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕氏
さくらインターネット代表取締役社長の田中邦裕氏
6年後の2005年には、東京証券取引所マザーズ市場への上場を果たす。
そこからM&Aにより事業を多角化するが、子会社の業績不振から、一時は債務超過に陥ることになった。当時を振り返って、「伝える」ということの大切さを強く説く田中氏。その失敗の経験をひもとく。
ロボコン少年、高専で学生起業
私は1978年、大阪の生まれです。テレビでNHKの「ロボットコンテスト(アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト:高専ロボコン)」を観て「将来は高専に進学をして、ロボコンに参加したい」というのが、小さな頃の小さな夢でした。